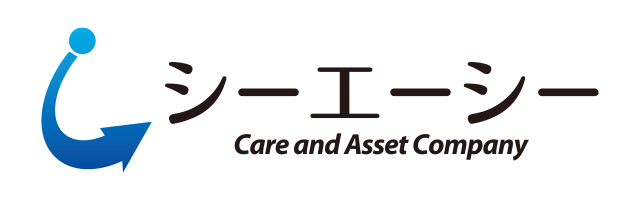最近、子どものいない叔父さん・叔母さんの介護についての相談が年々増えています。甥っ子さん、姪っ子さんとしては子供のころからお世話になっていたからという思いや親戚としての責任感もある一方、介護という大きな負担を負うのは簡単なことではありません。今回は、叔父・叔母の介護について分かりやすくお伝えします。
目次
まずはモヤっとした気持ちを“言語化”してみよう
「どうして私がやるの?」
「今までそんなに近しくなかったのに」
「甥や姪なら私でなくても」
――そう感じるのは当たり前です。
私自身、最初に電話をくださる姪御さんや甥御さんから、この言葉を聞かない日はありません。
☑ チェックリスト:あなたはいま何に戸惑っている?
- 費用をどこから捻出するのか想像がつかない
- 介護サービスや施設の種類が多すぎて選べない
- 相続や不動産のことを話題に出すのが気まずい
- 「断ったら冷たい人間だ」と思われそうで不安
4つのうち1つでも当てはまったら、専門家に相談するべきサイン。
ひとりで抱え込むと、“罪悪感”と“おカネの不安”のダブルパンチで動けなくなります。
ケースで学ぶ――
先日、都内の相談員さんからの依頼で、夫婦で老人ホームに入りたいという方のお手伝いに伺いました。
同席していたのは姪御さんとそのご主人でした。
高齢の本人たちには子供がいない、とのことでした。
会話をお聞きする限りそれほど距離の近い関係ではなく、敬語で話をされていたことから小さいころに親しかった様子でもありませんでした。
子供がおらず、身の回りのこともあまり整理せずに夫婦で足腰が不便になるまでここまで来てしまったようです。
奥様は認知症の症状が出始めており発言が二転するようですが、幸いご主人はまだ話がかみ合います。
希望としては、
「ホームに入居したら必要なくなる自宅を売却しそのお金でホームの施設利用料を賄っていきたい」ということでした。
いくつか気になることもありました。
・自宅以外に売れない地方のリゾートマンションを所有している
・ご先祖の墓の整理(墓じまい)をしないといけない
ということでした。
ご自宅のなかはまだ調査できていませんが、家具や家財、生活用品なども残ったままと思われます。
このようなことを整理して子供や親族に迷惑をかけないようにするのが「終活」ということなのですが、高齢になっても日々の生活に追われていたり体調を悪くすると整理ができそうでできないものです。
遠い関係の甥や姪ともあまり会話をしてこなかった、という話もよく聞きます。
こんな状態で、叔父や叔母から甥や姪が「後は頼む」と言われてしまうと
やはり「なぜ私が?」という気持ちになるのは当然です。
叔父・叔母介護の難しさ
親と叔父叔母では距離感が全然違います。
仮に甥や姪が相続をする立場であったとしても、
あまり資産や財産といったものにはタッチしたくないというのが心情のようです。
あまり乗り気ではないという場合もありますが、
ご本人に他に頼れる方もいないのでしたら、
なんとか落ち着くところまでは手伝ってあげてほしいところです。
ですが、この「なんとか落ち着くところ」というのが見えづらいゴールになります。
そこで大事なポイントは3点です。
1. 「おカネの流れ」を見える化する
2. 専門家を頼る
3. 報酬を受け取る
1.「おカネの流れ」を見える化する
親子関係と違い、叔父・叔母であれば他の親族とのかかわりもあります。
その中で一番大きな要素になるのが「お金」です。
事前に必要な資金を洗い出す、実際の費用を記録しておく。
これだけでもトラブルを避け、相談しやすくなる武器となります。
(1) まず“月額キャッシュフロー”を計算
- 年金収入・家賃収入など(+)
- 施設の月額利用料・介護保険サービス自己負担分(-)
- 医療費・お薬代・日用品・お小遣い(-)
- 自宅等の固定資産税(-)
(2) 次に“イレギュラー支出”を書き出す
- 自宅や別荘のリフォーム・解体
- 墓じまい・仏壇処分
- 相続税・贈与税
“見える化”さえできれば、介護慰労金や委任契約の報酬をいくら支払えるかが計算できます。
2.専門家を頼る
特に叔父叔母の介護では、積極的に専門家を頼っていただきたいと思います。
内容によって、弁護士、税理士、司法書士、行政書士、不動産業、保険代理店などがあります。
ごみ処分業者や整理やさん、買取屋さんなども関わることもあります。
そのような方々の意見を伺ったり、周りの経験者からのお話を聞いて
ヒントを見つけていただきたいと思います。
「成年後見制度」の話が前に進むかもしれません。
また、いつもお世話になっているケアマネジャーなども多少お分かりなることもあります。
3. 報酬を受け取る・目安
私が立ち会った姪御さんたちは、みなさん最初は「お金なんて・・」とおっしゃいます。
でも、半年もたつと介護費の立替え・有給の消化・夜間の呼び出し**でヘトヘトになり、
「最初からきちんと決めておけばよかった」と悔やむパターンがほとんど。
報酬の目安
報酬の目安ですが、たとえば行政書士や司法書士など、正規の後見人が「身上監護」「財産管理」という2つの業務を行う場合、ひと月あたり、おおよそ2~3万円の報酬をもらい受けることが多いです。目安の1つになります。
といっても、だいたいの場合、身の回りの世話ややりとりにあたって本人のところに向かうのは月に1回程度です。
ヘトヘトになるほど呼び出されたり多くの用事があるようですと、もう少し貰い受けてもよいように思います。
ちなみに「身上監護」とは、身の回りの世話や契約手続き、行政への書類提出や証明書等の入手の代行になります。
「財産管理」はその名の通り、お金や不動産の管理をすることですが、不動産の管理というと納税やリフォーム、空室の賃貸募集などまで入ってくることもありますので、ここでは”ごく簡単な範囲まで”というイメージです。通常は本人の口座の記帳や、低額のお金の出し入れ、月1回の振り込み手続き程度が考えられます。
このように、ちゃんとした報酬のやりとり(金銭の授受)が解決につながる場合があります。
「叔父や叔母に月々面倒をかけられてしまうけど、それなりに少しでももらえるなら気持ちよく手伝ってあげられるかも」というかたも多いです。
そして、ちゃんと世話をしてあげる代わりに、存命のうちに遺言書を作るなどして、甥や姪がちゃんと相続資産という〝報酬〟を受け取れる話が組み立あがるのであれば、甥や姪も「全く協力しないわけでもない」となるケースもあります。
要は、高齢者である本人にそのような心得があるかどうかにより周りの協力体制が変わってきます。
「子供がいないばかりに甥や姪に迷惑をかけてしまうから、せめてものお礼に」という気持ちが大事なようです。
内容によっては、十分に報酬をもらうに値するだけの作業や事務手続きを甥や姪がすることもあります。
甥や姪側から金銭を要求することはとても難しいことですので、相続や後見に絡む専門家から話を切り出してもらうなども1つの手です。
「お金の話は専門家から切り出す」――これだけで、家族間のギクシャクは感覚的には おおよそ8 割減ります。
どうしても無理だと思ったら
「介護は無理、でも放置もできない」
そう感じたら、まずは社会福祉協議会の生活支援員にお願いをするところから考えてみてください。日常生活自立支援事業と呼ばれるパッケージのサービスがあります。
それでも足りないようでしたら、成年後見人を立てたいという相談を司法書士や行政書士の先生にしてみるのが良いと思います。
まとめ:あなた自身が潰れないことが、最良の“親孝行”ならぬ“叔父孝行・叔母孝行”
- 断ってもいいし、引き受けてもいい。
- 引き受けるなら、お金の見える化・専門家の活用・報酬の3点を常に意識する。
- 迷った瞬間にプロに丸投げして OK。あなたが元気でいることこそ、最終的に叔父さん・叔母さんの安心につながります。
私たち「老人ホームの相談窓口」では、施設選びのお手伝いだけでなく、こうした手続きやお金・不動産の話まで幅広くサポートしています。
▼相談を検討している方へ
【無料配布中】
\マンガでわかる!老人ホームの相談窓口/
「引受人がいない」「費用が心配」「施設選びに失敗したくない」そんな悩みをマンガでわかりやすく解説!
LINEで今すぐダウンロードできます👇