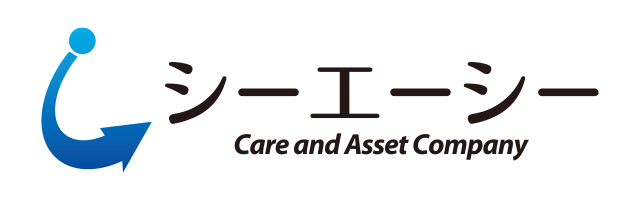甥や姪にあたるご親族のかたが子供のいない叔父叔母の老人ホームを探すお話をよく伺います。
ホーム探しのお手伝いをしながら、ご親族の方の発言からよく感じることは、
「どうして私がやらないといけないの?」
「今までそんなに近しくなかったのに」
「甥や姪なら私でなくても」
といった気持ちです。
そんなかた、いらっしゃらないでしょうか。
そして、必要なことはホーム探しだけではない、というケースがとても多いです。
主に整理をしておかなければいけない話題
主に整理をしておかなければいけない話題を記載しますと、
1 今後の住まいのこと(老人ホーム探し)
2 今後のお金の工面のこと(年金その他)
3 資産の把握・管理(現金・預金、株式や債券(証券口座)、不動産など)
4 身元引受・身元保証
5 成年後見・遺言
6 家の処分や片付け
などがあります。
順番に見ていきたいと思います。
1 今後の住まいのこと(老人ホーム探し)
老人ホームを探す(見学する)主人公は「ご本人」「子供」「兄弟・姉妹」「甥・姪」がほとんどです。
そのなかで、本人の判断能力が弱かったり、動けなかったりすることで、見学をする役回りがご家族に回ってきます。
どの場合も、本人が見て判断できればむしろ楽なのですが、資産や年金を調べて予算を考えてあげたり、ケアマネジャーからの注意事項(医療行為など)、健康なころの本人の気持ちを汲み取ってホームの雰囲気を感じたりしながら選ばれることが多いです。家族や親族が先に見学をして、おおむね候補を絞ってから本人を連れて行ってあげることも多いです。
甥や姪のかたが動く多くの場合は、実子がいないか疎遠野関係であり、かつ本人の能力が衰えてきていることが多く、上記のように候補を選んであげたり、場合によってはホーム決定まで行ってあげたりすることが多くあります。今後の自分たちの負担や負荷を軽くするために、なんとかホーム選びまでできると「一区切りついたぞ」と考える方が多いです。
2 今後のお金の工面のこと(年金その他)
叔父や叔母が健康なころからお金や資産に関する情報をよく知っている方はあまり多くありません。一緒に生活していれば情報も入ってくるものですが、甥や姪のかたが同居している方は多くなく、おのずとお金や資産の情報はわからないものです。
本人が生活にご不便をされるようになってから「通帳見るけどいい?」とか「証券口座とかどこにあるの?」、「土地や建物の権利証はあるの?」といった会話が発生してきます。そのなかで、ざっくりとした財産のイメージがわかってきます。
そのなかで、今後もらえる年金といまある財産を机の上に並べてみて、そこから今後の出費を計算してあげる必要が出てきます。ホームに移る場合の主な出費としては、
・ホームに入所するときに払う一時金
・入所後のホームの月額施設利用料
・所有している土地や建物の固定資産税
・自宅のリフォーム費用
・医療費・お薬代
・利用する介護の保険料(ホーム利用料に含まれる場合もあります)
・整髪費
・消耗品費(おむつ・ティッシュ・洗剤など)
・娯楽費
などがあります。
将来のホームの入居期間を考えながら出費の総額を把握し、あわせて年金の額や貯金の額、株式や不動産の売却額などを考慮して、計画的に試算することが大事です。
「ちょっとそこまで見てられない」というかたはファイナンシャルプランナーや当社のような老人ホーム相談窓口に問い合わせることになります。以前に、「ホームに入居したけれども資金が底をつき、急遽安い老人ホームに引っ越さなければいけない」というかたにお会いしました。疎遠な甥が何も手伝ってくれないとのことで、その施設の長のかたが頑張って対応をされていました。
せっかくなので、資金繰りのところまでは「ホーム探し」の一環として、留意してあげてほしいと思います。
なお、入居期間についてはこちらのページもご参照ください。
甥や姪のかたで、法定相続人に該当するかたは、相続にあずかる場合もあります。
「世話をしているからすこしぐらいは相続したい」という気持ちも間違ってはいません。このあとの5 後見契約・遺言もあわせてご覧ください。
3 資産の把握・管理(現金・預金、株式や債券(証券口座)、不動産など)
現金や預金は財布やタンス預金、銀行の通帳を探すことでおおよそ把握することが可能ですが、株式や債券は証券についての取引残高報告書や各種郵送物で確認したり、証券会社の窓口担当や営業担当に連絡を取ったりすることで確認することになります。ですが、子供ならまだしも、甥や姪ですと本人や家族ではないことから、証券会社が情報の開示に応じない場合があります。その場合には証券会社から本人に対して、情報開示に関する電話での確認を求められたりします。今後の生活にあたってはこれらの資産をあてにすることが多いと思いますので、やはり資産の把握や管理についてもある程度関与いただきたく思います。
4 身元引受・身元保証
本人がホームに入居するときに、「身元引受人」を決めていただく必要があります。本人の生命に関わることや病院やホーム側で決められない緊急の話題がある場合の最初の連絡先となります。また、死亡時にご遺体を引き取る責任者でもあります。たとえば、ホームで体調が悪くなってしまい緊急入院することになったときも、病院での入院手続きや退院時の支払いなども行うことになります。
体調が悪くなければ頻度は多くないのですが、医療関係者や介護関係者が「これは重要」と判断したときに連絡をする大切な役者です。いろいろと大変なことではありますが、身元引受人は甥や姪の多くのかたがサインをされています。
一方、身元保証(人・会社)というのはご家族、ご親族がいらっしゃらない「おひとり様」などがホームに入居する際、ホーム側が今後も間違いなく施設の利用料を払ってくれることを約束してくれる人として必要な役者です。入院する際の病院から求められる場合もあります。身元保証を求めないホームもまれにあります。
どうしても「身元保証」を引き受けたくない場合には、有料でその身元保証のサービスを提供する会社があります。一般に「身元保証会社」と呼ばれます。
この身元保証会社は、緊急時の連絡先になったり医療費の支払いなどを代行したり、さらに日々の生活支援など様々なサービスを提供してくれます。
資金的に余裕のある方の場合は身元保証会社を利用することもできますが、遺体の引き取りなどの「最後のお仕事」は身元保証人ではなく身元引受人の仕事となり、保証会社の業務対象外となっている場合が多いです。
5 成年後見・遺言
成年後見は正しくは「成年後見制度」と言います。細かい話題はこちらのページ(後見人の仕組みがわからない)でご確認いただきたいのですが、主に本人が認知症になるなど判断ができなくなったときに、本人の意思を尊重しつつ本人になり代わって意思決定をできるようにする制度です。
後見人とは、本人がお金や資産を保有していて、それを本人の今後の生活のために利用しなくてはいけない場合に、高額のお金を引き出して支払ったり、株式や債券、不動産などを売却して、ホーム入居の一時金に充てる場合等に、その手続きを代行できる人になります。
その他、自分が好意で面倒を見てあげているのに、他のご親族から「なぜあなたが通帳を預かっていたり資産の管理をしているの?」と指摘をされる場合があります。このような場合にも、堂々と管理などをしてあげるために後見契約を作成することがあります。
甥や姪のかたにとって、後見契約は「(自分はあまり関心がないけど)本人の生活のために作ってあげたほうがいい」という場合と、「今後面倒を見てあげるために、自分のためにも本人の生活のためにも作ったほうがいい」という場合があります。
なお、遺言書は資産を受け継ぐことを本人に約束してもらう手段です。甥や姪にとっては実子でないのに面倒を見てあげることになりますので、素直に「面倒を見てあげるから、相続の時は恩恵にあやかりたい」という気持ちを形に残す手段でもあり、後見契約とセットで作成されることも多いです。専門家とともに計画的に作成を検討してみましょう。
そもそもの話題ですが、放置をしておくと本人の能力の低下に伴い大切な本人の資産を有効に活用できなくなる場合がありますので、後見契約や遺言書については、司法書士や弁護士、行政書士などの専門家と相談をすることをお勧めします。
6 家の処分や片付け
いまやもう住まなくなってしまったご自宅や不動産が放置されていることがよくあります。本人がアパートやマンションなどを賃借している場合には、家具や生活用品などを整理して処分をし、大家さんに明け渡しをすればよいことになりますが、家を所有している場合には手放すか利用するかなどの方針を考えなくてはいけません。
処分してお金にして生活資金にするのか、念のために将来戻れるようにするために継続して保有し税金を払い続けるのか、家族が利用するのか、あるいは第三者に賃貸するなどを考えることになります。
家具や生活用品の処分を家族や親族が行うことは意外に大変です。その理由はこちらに詳しく記載しています。
多くの場合、放置をしておいても税金を払うだけになり、賃貸収入が入るチャンスを見逃したり家の劣化を進めてしまったりすることになり、良いことにはなりませんので、上記のなかから方針を決めることをお勧めします。
以上になります。
実際に相談に来られた姪のかたのお話しも載せていますので参考にご覧ください。